講演会講師インタビュー|大ヒットドラマ『TOKYO MER』を手掛け、現在は大映テレビの社長としてドラマ制作現場を牽引するプロデューサー・渡辺良介(わたなべ りょうすけ)氏にインタビューをしました。
- 目次
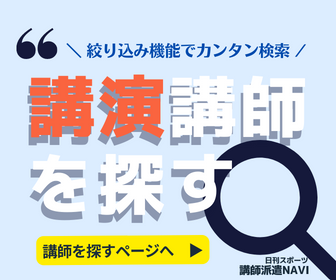

ドラマプロデューサーの仕事とは

ドラマの現場を長年支え、数々のヒット作を世に送り出してきた渡辺良介氏。彼が考えるドラマづくりの原点とは何か。その答えを探るため、まずは「プロデューサーの仕事」とは何か伺いました。
渡辺
ドラマを作るにあたって…まず、最初に企画をします。どんなドラマを作るか。今は原作のドラマが多いですが、この漫画をドラマ化したい、この小説をドラマ化したいっていう企画から始めます。こちらは制作プロダクションという立場なので、それ(企画)をテレビ局に売り込みます。それで企画が決定したら、具体的に制作に入っていくんですけど、その段階でやることが、まずシナリオを作ること。脚本家を決めて、シナリオライターと一緒にどんな話にしていこうか、ということを決めます。あとキャスティング。どなたに主演をお願いするか、相手役はどなたにするかというのを決めます。あとはスタッフを決めます。監督は誰にしようか、カメラマンは誰にしようか。もちろん、一存では決めませんが、相談しながらスタッフ編成をします。それで番組全体のチームが出来上がるので、そこからの主な仕事はシナリオに対して責任を持つということ、予算に対して責任を持つこと。あとは番組のクオリティー管理といいますか、最終的に撮りあがってきたもの、撮影中に関しても気になるところは意見を言ってですね、納品物に対して責任を持つということが、プロデューサーの主な仕事になります。
――
多くの視聴者はテレビドラマというと、その放送局が制作していると思っている人がほとんどですが、実際は放送局がすべて番組を作っているわけではなく、関連の映像制作会社と共同で、あるいは外注しているケースもあるわけですよね。渡辺さんの場合は、大映テレビという映像制作会社に入社され、そこでドラマプロデューサーとして仕事し、その作品がTBSやフジテレビなどの放送局で放映されてきた、ということですね。
渡辺
その通りで、テレビ局自体が作る、いわゆる局制(作)というものもあれば、局制の中にも我々のようなプロダクションが協力して作るようなものもあれば、完全に委託して作るものもあれば…。私の場合は、一緒に作ることもあるんですが、いずれにせよ中心になって作っていくというような立場にあります。
――
ドラマプロデューサーとして、一番大事にされていること、ドラマを制作する上で重要なファクターとは何なのでしょうか。
渡辺
ドラマだけでなく、我々テレビ屋はですね、基本的に「視聴者の方々が喜ぶためにある」という自負、矜持がありますので、何より「視聴者が何を喜ぶのか」「見て良かったな」と思う番組作りを心掛けるのが一番かなと思っています。
「TOKYO MER」誕生の背景

数々の作品を手がけてきた渡辺氏に、これまでで特に印象に残っているドラマについて尋ねると、迷うことなく一つのタイトルが挙がりました。ここからは、その背景に迫ります。
――
自身が関わったドラマはどれも子供のように愛おしい存在だと思いますが、その中でも印象に残っているドラマを挙げるとしたら…ありますか。
渡辺
「TOKYO MER」ですかね。経緯としましては、「テセウスの船」というドラマに参加し、その時に鈴木亮平という俳優に出会い…。「テセウスの船」はおかげさまで(視聴率が)好調に推移したんですけど、ちょうどオンエアが終わるあたりにコロナが流行しまして、打ち上げもできなかったんですね。日本がロックダウン状態になった中、TBSの盟友であるプロデューサーと「次も鈴木亮平を主演で何かやりたい」となった時に、まあ「何をやろうか」という脚本の中で、ちょうどコロナ禍で医療従事者が大変な思いをして患者のため、国民のために頑張っているという姿を見て、是非そういう方々を主人公にしたドラマを作りたいと思って立ち上げたのが「TOKYO MER」でして。それが本編の中でも最後、実際に医療従事者の方の写真をお借りして、実際の我々の身の周りにいるヒーローとして登場してもらったんですけど、それが医療従事者の方から感謝といいますか、お言葉をいただいたことが印象に残っています。
――
ドラマ「TOKYO MER」での鈴木亮平さんという役者の存在は大きかったですか。
渡辺
「TOKYO MER」の北見という主人公は、鈴木亮平さんに似たところがあって。もちろん、鈴木亮平さんをイメージして作った役なので似るのは当然なのですけど(笑)。かなり気配りもできて、チームを統率することができる、非常に素晴らしい俳優だと思っています。
テレビを愛した少年時代からプロデューサーへの道のり

幼い頃からテレビに魅了されてきた渡辺氏。三重県で過ごした“テレビっ子”時代の原体験、大学で得た気づき、そしてプロデューサーを志すに至るまでの歩みについて伺いました。
――
現在50歳、三重県松阪市出身で早大教育学部を卒業され、大映テレビに入社されました。大映テレビのHPでご自身のことを紹介されていますが、そこには「テレビが好きなんです。子供の頃からずっと。今でも。」との書き出しで思いを綴っておられます。テレビがお好きなんですね。
渡辺
そうですね、テレビが好きでした(笑)。今でこそインターネットとかSNSとかユーチューブとかありますけど、当時の娯楽はテレビしかなくてですね。三重県出身なんですが、土曜の昼間にやっている吉本新喜劇の放送が大好きで。「笑い」って人を幸せにするじゃないですか。まぁ、そういうお調子者の子供だったんですけど、テレビの向こう側がすごく気になってですね、そっちの人に憧れを持ったんですね。それが小4か、小5ぐらいの時だったですね。あっち側にいきたいなあと思いながら、でも田舎で情報もなく、それでもまぁ少ない情報をたどって、テレビ局に行けば番組が作れる、テレビが作れる、という思いで東京へ出てきてですね、今の会社に縁があってそのまま続けている感じなんですけど。
――
渡辺さんが子供の頃に刺激を受けたテレビ番組って、どんな番組でしたか。
渡辺
好きだったのは、僕は「あぶない刑事」ですね(笑)。毎回録画して見てて…。あとはお亡くなりになりましたけど中山美穂さんの「毎度おさわがせします」とか。当時のTBSのドラマも好きだったし…。でも、僕はドラマが好きだったというわけでもないんです。ドラマも見ていましたけど、本当に「テレビ」が好きで、それでドラマを作りたいというよりも「テレビ」を作りたくて、今の世界に入ってきたというのが正直なところなんです。
――
中学、高校、大学の頃はどんな学生だったのですか。スポーツとかは何かされていましたか。
渡辺
とくに(スポーツとかは)何もせず、ずっとテレビの仕事をしたいなと思っていましたので。放送研究会とかにも入らなかったんですけども、ずっとそこ(テレビの現場)で働くこと、就職をしたいと思っていましたね。
――
大好きなテレビの仕事を職業にしたいと意識し始めたのはいつ頃ですか。
渡辺
なので小4か、小5ですね。その時からずっと…です。親は医者にしたかったみたいなんですね、僕を。単純に、(親は)田舎の人なんで、安定するし、立派な職業だからというところで。親は医者でも何でもないんですけどね。でも僕はどうしてもテレビの仕事をしたいんだって…で、大ケンカしながら、東京に出てきましたね。それがまあ、回りまわって、「TOKYO MER」という医療ドラマを作るというのは、なんか因果なもんだなと思いながら、作っていたんですけど。
――
制作側、裏方ではなくて、ドラマを演じる側、役者に興味を持たれたことはなかったですか。
渡辺
まったくないです。身の丈を知っているので(笑)。自分に向き、不向きというのがあるので。ただ、プロデューサーと監督、ディレクターとかの職種の違いというのは、当たり前ですけど、分からずに東京に出てきて。最初はいわゆる監督って格好いいなと思って出てきたんですけど。早稲田大学って、非常にそういうエンタメを目指す人がたくさん来る大学で、当時、堺雅人さんが(早大で)同世代で、お芝居をされていたんですけど。そこの劇団の芝居を見に行ってですね、打ちのめされて(笑)。「こんなハイセンスな演出は僕にはできない」と思った時に「プロデューサーっていう仕事だったら、そういうクリエーターたちと一緒に何か作っていくことができるんじゃないか」と思って。それでプロデューサーという職種を意識したっていう、それが大学3年生ぐらいの時ですかね。
――
大映テレビに入って、すぐにプロデューサーとして仕事をされたのでしょうか。
渡辺
「アシスタントプロデューサー」を経て「プロデューサー」へ進むのですが、わりと「プロデューサー」デビューは早かったんですね。ドラマの場合は「プロデューサー」と「ディレクター」というのは明確に仕事が違うので、「アシスタントディレクター」をしてから「アシスタントプロデューサー」をやって「プロデューサー」という…わけでもないですね。
作品づくりの中心にあるもの――ヒットから見える共通点

多くの作品を手がけてきた渡辺氏が大切にしていることは何か。ヒット作に共通するポイントとは何か。そして、現場でヒット作を生み出す一方、経営トップとして会社を率いる中での渡辺式の極意についても伺いました。
――
大映テレビに入社して50歳まで夢中で走り続けてこられたと思いますが、ヒットドラマを生み出すため、いろんなことにアンテナを張られていると思います。膨大な情報が氾濫する中で、何を優先してインプットしていくか、渡辺式の極意ってあるのでしょうか。
渡辺
今、どんなマンガが流行っているかとか、どんな小説が流行っているかとか、気にはしますけど、やっぱりドラマって本質的には今の時代も、平成の時代も、昭和の時代も、描かれるテーマは変わってないと思っていて。結局「人間」を描くので。その「人間」の考え方というのは時代、時代で変わったりするじゃないですか。まぁ男性と女性の在り方とかも変わってきているので、友人とかと居酒屋へ行っても、隣の席の会話とか聞きながら、「今の時代ってこういうふうに考えるんだ」とか、価値観の変容を見逃さないようにするというのが、一番大きなことですかねぇ。
――
ヒットドラマを生み出した経験の話は、おそらく他業種でも参考になるように思います。商品やサービスをヒットさせるコツにつながると思うのですが…。
渡辺
僕らが作るのはテレビドラマなんで、ドラマをベースでお話させてもらうと、まず一番大事なのが「どんなドラマか」なのかが分かること、「イメージしやすいもの」であるということ。「TOKYO MER」で言うと、「救命医がオペ室を飛び出して」「事件現場、災害現場に乗り込んで行って」「熱い思いで救う」というのが、一番根幹のログラインみたいなところであって。そこをまず明確にして、それが面白いかどうかっていうことですね。いろんなアイデアを盛り込もうとするのが開発者の思いとしてあると思うんですけど、結局「何なの?」というような曖昧にならないようにすること、それはプレゼンの上でもそうですし、番組を宣伝していく上でも、なるべくシンプルで強いメッセージを考えるというのが一番のコツかなと思っています。
――
メーカーなどの商品開発にとどまらず、サービス業、自治体などの町おこしのヒントにしたいと思う方々にとっても、今のような話がヒントになってくるわけですね。
渡辺
そうですね。「いろいろ」「あれもあるよ」「これもあるよ」というのを、たまにチラシで見かけるんですけど、「一番面白いのは何か?」というのを、勇気をもって打ち出すというのが大事で。もっというと、僕は結果としてヒットしてきただけで、ヒットドラマを作ろうと思って…作りたいですけど、それができたら10倍ぐらいのヒット作を僕は作っていることになるので(笑)…結果的に当たったということでしかないんですけど。長年仕事してきて思うのは、それは僕だけの法則ではなくて、近作では「国宝」(映画)もそうですけど、誰か1人のものすごい熱量というか、情熱が作品に乗り移った瞬間、それは必ず届くっていうのが、今の僕の「哲学」というか、生意気なんですけど、「思い」としてありますね。だから「国宝」でいうと、李監督の思いも含めて「吉沢亮」「横浜流星」という若い2人が本気で歌舞伎に取り組んだというのが、やっぱり画面を通して観客の胸を打つんだと思います。
――
実はドラマプロデューサーとして現場でご活躍される一方で、2019年からは大映テレビの社長さんも務められています。ヒットドラマプロデューサーと社長業の二刀流、大変じゃないですか。
渡辺
最初のうちはうまくいかなかったです。プレーヤーの意識が強かったですし、プレーヤーを周りから求められたので。プレーヤーとマネージャーの二足の草鞋(わらじ)って、なかなかうまくいかないというか…。うまくいかない理由はプレーヤーという意識が強い以上、仲間を、部下をプレーヤーとして見るので、プレーヤーとしてものを言うと、やっぱり反発も食らうし、うまくいかないという…。ただ年齢もあって、この先テレビをよくしたい、面白くしたいという時に、1人じゃできないので、仲間を増やそうと思った時に、同じ仲間だし、自分が歩んできた道を部下たちが、社員たちが歩んできているので、そこに対して寄り添うみたいな気持ちでマインドチェンジしたら、うまくいくようになりましたかね。
――
若い世代を中心にテレビ離れも進んでいます。自称テレビっ子として、危惧されていますか。
渡辺
危惧してますね、テレビ離れ。うちの娘を見ていても実感しますし。ただまあテレビという産業自体が60年そこそこで、テレビができる前までは映画が全盛だったわけで、いわゆる産業がテレビにシフトしたっていうタイミングで60年経って、今は配信だとかネットフリックス、アマゾン、あとユーチューブが出てきたっていうのは、時代の流れっていうのがあるのかなぁっていうふうには思っています。我々プロダクションでストーリーを作るという仕事をしている以上は、そうしたメディアが変わってもドラマ自体がなくなるわけではないので、メディアがチェンジしたというふうにはとらえているんですけども。ただ「テレビっ子」としては、テレビに踏ん張ってほしいというのはありますし、いろいろ思うところありますね、確かに。
――
やっぱり良質のコンテンツを作るというのが何より大切で、今後向かわれていくところもそこですかね。
渡辺
おっしゃる通り、それに尽きると思うんですよね。結局、作り手が、面白いと思うもの、伝えたいと思うものをしっかり作るということが一番だと思っています。テレビの視聴率自体はどんどん右肩下がりで落ちてきていますけど、それでもドラマだけ見ると、そういう思いにあふれた作品というのはヒットするんですよね。ちょっと前の鈴木亮平と長澤まさみの「エルピス(―希望、あるいは災い―)」しかり。あれだけ難しいテーマでも、作り手が情熱を持って作れば届くっていう…それがまあ、その「救い」なのかなと思います。時代が変わって若者が変遷していっても、そこは受け取ってくれるというのが、希望なのかなとも思います。
若者へのメッセージ――夢、AI時代、そしてエンタメの未来

エンタメ業界で長年活躍してきた渡辺氏が若者たちに向けて伝えたいメッセージは何か。夢に対する考え方、AI時代におけるエンターテインメントの未来――豊富な経験に基づく示唆に富んだ視点を伺いました。
――
渡辺さんの講演テーマの中に「エンタメ業界を目指す若者たちに」というのがありますが…どんなお話をされるのでしょう。
渡辺
今、「ティックトッカ―になりたい」とか、「ユーチューバ―になりたい」とか、いろんな方がいらっしゃると思いますが、昔と比べたらかなりチャンスがあると思うんです。自分で発信できるので。だから諦めずにやればいいし、特別近道はないという話ですかね。すべての仕事って、誰かが感謝して初めて対価であるお金が発生するので、それは芸能の仕事であっても、そうですよ、ということですよね。「有名になりたい」「チヤホヤされたい」っていう初動の欲っていうのは、別に全く否定はしないですし、昔から芸事を目指す方っていうのは、そういう思いがあったと思うんです。それをまあ仕事としてみて、仕事が来るということはプロフェッショナルとして今の自分に何ができるのかということをしっかり考えて、それを意識して自分なりに発信していくということ。そうすれば、いつか目に留まる、チャンスが来るのかなと思います。
――
夢を持てない若者が増えていると言われていますが、どう思われますか。
渡辺
学校の先生に「夢を持てない若者たちが多い」というのを聞いて、それがずっと僕は残っていて、自分だったらどんな話をするだろうかなと考えていたんですけど。ドラマのプロデューサーとして、シナリオを一緒に作っていく人間としてまずあるのはすべての人間を肯定するという作業から入るんです。ドラマの主人公って、聖人君子じゃないことの方が多い。「どこか欠けていたり」とか「どっかがダメだったり」する、それでも何かを一生懸命やるっていう人が多くて。で、夢を持てない子供たちに何を話すかという時に、「何で夢を持たなきゃいけないのかな」と。「夢って何なんだろうな」「夢を持たなきゃいけないって話すことが、かえって子供たちを窮屈にしているんじゃないかな」と、思ったりもするし。でも夢を持つことはすごく素敵なことで。だとすると「夢を持つにはどうしたらいいのかな」って考えたんですよね。例えばドラマに置き換えると、「ROOKIES(ルーキーズ)」だとするなら、諦めて自暴自棄になっている不良少年たちに、川藤(ドラマで川藤幸一役の佐藤隆太)は「野球をしよう」って言いますよね。野球をして、みんなで同じ目標を持つことで、それがやがて夢に変わるっていうプロセスがあってですね。結果的に夢を持つことは素敵なことなんだし、素晴らしいことなんだけど、それはそういうこと、プロセスなんじゃないかとか、何か違うメッセージの投げ方があるんじゃないかなとか、思いますね。
――
ハリウッドなんかでも、AIを使ってやってもあまりヒットしないって言いますね。
渡辺
我々エンターティメントであり、多額の資金で映像を作っているのでもちろん、ヒットさせることはとても大事なことで。今ハリウッドなんかはAIが発展しているので、プロントという基本的な物語の粗筋をAIにかけてヒット予測をさせるっていうのがあります。それはいわゆるマーケティングリサーチ的なものなんですけど、物語のテーマだったり、主人公のキャラクターだとか、物語の展開でヒット予測をするというふうなシステムがあると聞くんですけどね。それは確率70%とか、80%とかしか出ないんですよね。AIなので120%って出ない。つまり法則にあてはめて、方程式にはめて作っても80%のコンテンツでしかないというふうに僕は考えていて、それよりも残り20%のところに、120%、150%、「国宝」級の大ヒットが埋もれてるんじゃないかなと思うんですよ。実際、「国宝」って、歌舞伎というテーマで、歌舞伎なんて見にいく若者なんて一人もいないし、今の熟年層だって歌舞伎とは遠い世界で、しかも3時間を超えて、あの作品があそこまでヒットするというのは、やっぱり誰も予測できなかった。そこがエンタメの難しいところでもあり、面白いところでもある。それにはやっぱり誰かひとりの熱狂が人々を巻き込んでいくというのが、この世界の、エンターメント業界の特徴なのかなって思いますね。
――
渡辺さんの講演を是非聞いてみたい、興味がありますというお客さんに向けて、最後にメッセージをお願いします。
渡辺
私はテレビを主戦場にしていますので、聞きたい、見たいというご要望があれば、それに応えるのが仕事ですので、何でもオーダーがあればお話しできるようにするんですけど…。テレビドラマを見て、作ってきていると、結局は描くのは人なんで、自ずと人をよく観察するし、その人の人生を、シナリオを通して考えるので、人に対する思いというか、どうすれば人は動くか、リーダーたる主人公のどんな一言で人が動くか、どんなことでチームがバラバラになってしまうかとか、そういうことを日々考えています。具体的なヒットドラマの作り方だけでなく、ある意味人生訓というか自己啓発的なこともお話できると思いますので、もし興味がございましたらお声がけください。よろしくお願いいたします。
――
長時間ありがとうございました。
プロデューサー 渡辺良介 氏 インタビュー
渡辺良介 わたなべりょうすけ
ドラマプロデューサー、脚本家
1975年生まれ。三重県松阪市出身。 早稲田大学卒業後、「スクールウォーズ」「スチュワーデス物語」など多くのヒットドラマを制作する大映テレビ株式会社に入社。多くのテレビドラマの制作にプロデューサーとして従事する。片平なぎさ主演「ショカツの女」などの2時間サスペンスのヒット作も多く、TBS「魔王」で連続ド...

